手鋸(金鋸)
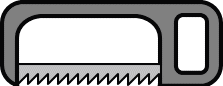 |
言うまでもなく「のこぎり」。材料を切断する工具です。ロボ研で使う金鋸の場合、押して切るように刃を取り付けるのが普通です。 |
パイプカッター
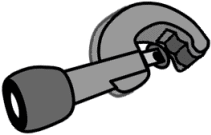 |
パイプを切る道具です。鋸のように「挽き切る」のではなく「せん断する」ため、切り口がギザギザにならずきれいな仕上がりになります。
ロボ研にあるパイプカッターは、ステンレスパイプを切ることができません。刃が欠けるのでやめましょう。 |
万力
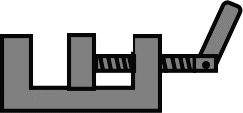 |
加工する材料を固定する工具です。左図は持ち運びができるタイプですが、作業場内の切り出しで使うのは普通、作業机に固定されているタイプです。
持ち運び型を使用するのは穴あけの時や、大会会場における作業等の緊急時です。機械科ならフライス盤の実習で制作するかもしれません。 |
手鋸(木鋸)
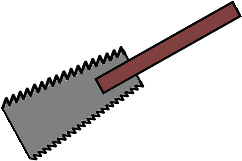 |
木工用の鋸。両刃タイプと片刃タイプがあります。のこぎりというと一般的にはこちらの方が知名度は高いでしょう。金鋸とは刃の向きが逆です。恐らく「引いて切る」方式は日本風と思われます。
両刃鋸の場合、刃の粗い方が木目に対して平行に切る「縦引き刃」、細かい方が木目に対して直角に切る「横引き刃」です。 |