手仕上げと穴開け
|
ロボ研でいう部材の手仕上げとは、ほとんどの場合「やすりがけ」を指します。
切削によって粗くなった部材の端面を、金やすりによって滑らかにし、バリを取って綺麗にし、扱いやすくします。
穴開けは言うまでもなく、ドリルを使って穴を開ける作業です。 |
工具・機械
やすり
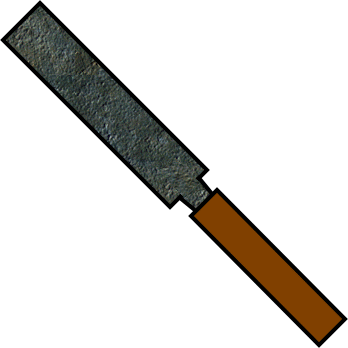 |
ロボ研で使うのは主に鉄製の「金やすり」です。目の粗さは様々ですが、粗目・中目・細目の3種類に適当に区別されることがあります。
他に、紙でできた「紙やすり(サンドペーパー)」水に強く丈夫な「耐水サンドペーパー」もあります。こちらは木材の仕上げに多く使われます。 |
ワイヤーブラシ
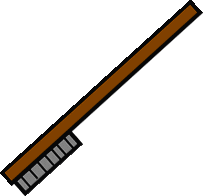 |
ブラシ部分が金属ワイヤー製のブラシです。
やすりの目に詰まった金属粉を取り除くのに使用します。 |
ドリル
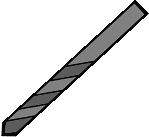 |
穴開け用の刃物です。
いろいろな材質があり、また表面がコーティングされているなど、穴を開ける対象によって使い分けます。当然性能と価格は比例します。大雑把に、
黒:アルミ・真鍮・非金属用
銀:ステンレス用
金:最高級品
と覚えておけばいいでしょう。 |
リーマ
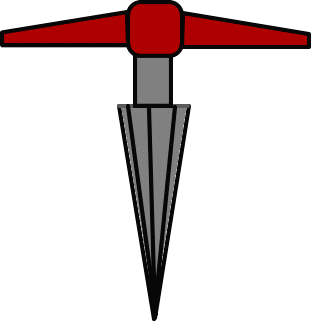 |
穴を広げたいときに使用する工具です。穴開け位置の精度は落ちるので注意。 |
| ボール盤 |
穴開け用の工作機械です。 |
|
通常部材の手仕上げ |
- 材料を万力で固定する。その際、仕上げたい面を水平にして取り付ける。部材が長いなど、水平にできないときは垂直に取り付ける。
- 片手でやすりの柄を握り、もう片方の手でやすりの先を持つ。
- やすりの面が仕上げる面と平行になるように当てる。
- やすりの先を持っている側の足を前に出し、鋸引きの時と同じように立つ。
- 脇を固定し、力を入れすぎないように注意して、膝の動きでやすりがけをする。鋸引きと同じく、押すときに力を入れる。
- やすり終わったら部材を万力から外し、部材の角にやすりを斜めに当ててバリを取る。部材内側のバリも取れるなら取っておく。
- 端面を斜めや丸形に仕上げる場合は、やすりではなく部材の向きを変えるようにする。
- 手ではなく膝を使って体全体でかけるようにする。
- やすりは常に顔より下の位置で使う。けがき線が見えにくいからと下からのぞき込まない。
- 力を入れすぎると仕上がりが汚くなり、やすりの寿命も縮める。
- やすりの目が詰まったときはワイヤーブラシで切り子を取り除く。手で払うと切り子が刺さる恐れがある。
- 仕上げる面は万力にできるだけ近づけて取り付ける。但し、仕上げの際やすりが万力に当たるほど近づけない。
|
部材の固定方法(真上から見た図)一例
×が付いているくわえかたは、やすりがけの際部材が変形する恐れがあるからです。
|
| ボール盤による穴開け |
- ボール盤のブレーカーのスイッチをONにする。
- ボール盤のチャック(ドリルをくわえる部分)を、チャックハンドルを使って緩める。
- ドリルを差し込み、チャックをしっかりと締め付ける。ドリルを手で軽く回しながら締めると中心に入りやすい。締めたら、チャックハンドルを抜くのを忘れずに。
- 本体のスイッチを入れてみて、ドリルがぶれていないか確認する。終わったらスイッチを切る。
- 材料を万力に固定する。アングルの場合当て木を使うこと。パイプの場合は当て布をする。
- ドリルと材料の距離が適切になるよう、テーブルの高さを調節する。
- スイッチを切ったまま静かにドリルを降ろし、ドリル先の位置合わせをする。ポンチ穴上にドリルを降ろしたとき、ドリルがずれているとわずかに横に動くので、よく見て正確に位置合わせをする。
- 左手で万力をしっかりと押さえ、右手で本体のスイッチを入れる。
- ゆっくりとドリルを降ろして穴を開ける。チャンネルや角パイは、上面の穴が貫通したら一度ドリルを上げて位置確認をする。
中実材など、切削量が多いときは途中で何度かドリルを上げて切り子を飛ばすようにする。
ステンレスなど硬い材料の場合、切削油を穴やドリルに差して潤滑・冷却をしながら少しずつ切削する。ドリルの種類に注意。
万力に穴を開けないように注意する。当て木・当て布に穴が開いても構わないが、ドリルが当て布を巻き込んで止まることがあるので気を付ける。
- 穴が開いたらドリルを上げてスイッチを切り、万力から材料を外す。
- 穴開けに用いたものよりサイズの大きなドリルを手で使ってバリを取っておく。
- 手を切らないように注意。特にバリ取りの時は気を付ける。
- ドリルはしっかりと固定する。緩いとドリルが材料にはまって取れなくなったり、チャックとの摩擦でドリル表面が削れたりする。
- チャックハンドルは使い終わったらすぐに抜く。忘れてスイッチを入れると非常に危険。
- 本体スイッチは左手側にあるが、右手でスイッチを入れること。万力から手を離すと振動で万力が動いてしまう。
- ドリルは材料に垂直に入れる。曲がるとドリルが折れる。パイプの穴開けは特に注意。
- 位置合わせや穴開けの時、ドリルを勢いよく降ろすとドリル先が潰れるので避ける。
- 貫通する寸前は送りを小さくする。そうしないと穴の形が歪む。
- 真鍮材の穴開けは、貫通の瞬間に材料がはね上がることがあるので、しっかりと押さえて送りもできるだけ落とす。
- 顔はできるだけ離す。直立の姿勢が望ましい。髪が長い人は帽子をかぶる。できれば作業用のゴーグルをかけると安全。
- 慣れて来たら万力を使わなくても良いが、まず万力を使った穴開けをマスターすること。また、パイプの穴開けは必ず万力を使う。
|
固定方法(真横から見た図)一例
板材は万力が使えません。回転しないよう、手でしっかり押さえましょう。
|
| 比較的大きな穴を開ける場合 |
- φ7以上の大きな穴を開ける場合、それより小さい径の下穴を開けてから徐々にドリルの径を大きくします。
- 穴は1mm位ずつ大きくしていきましょう。
- ドリルが暴れる危険があるため、送りはできる限り小さくします。回転数も落とした方が良いかもしれません。回転数はボール盤上部のカバーを開け、伝達ベルトの位置を変えることで調節できます。
- ボール盤に取り付けられるドリルはφ13までです。それ以上の拡大はリーマを使いましょう。リーマはちょっとした穴径調節にも使えます。また、円筒の中心に穴を開けるときは、旋盤を使うのも手です。
- ドリルを変える毎に穴の位置確認をします。
|
|
|