ドライバー
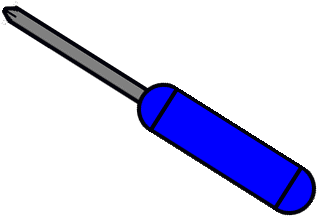 |
ねじ回しです。先端の形が+と−あります。ビスを回すとき使うのは普通+です。
・・・まあ小学生でも知ってますね。 |
ボックスレンチ
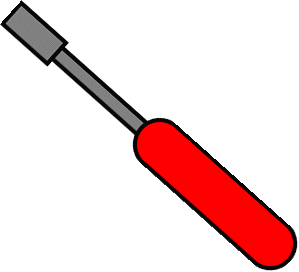 |
「ナット回し」です。先端にナット型の穴が開いています。
手で十分なことが多いですが、試合前の締め直しや、ねじ山にドライバーが届かないときナット側から締め付けるのに必要です。 |
十字レンチ
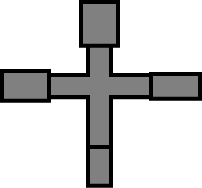 |
十字型の先端に、それぞれ異なるサイズのナットに対応した穴が開いたレンチです。ロボではほとんどM3のビスを使いますが、たまに違うビスを使うときに使います。ナットに大きなモーメントをかけることができるので、強く締め付けたいときにも使えます。 |
六角レンチ
 |
穴が六角形のねじを締めるときに使います。ロボ研ではギヤのイモねじを締めるために使うことが多いです。 |
ラジオペンチ
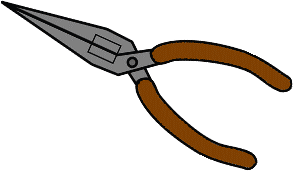 |
ナットの取り付け位置の関係でレンチが届かないようなときにこれで押さえます。その他細かい作業全般で指の代わりを果たす万能工具です。 |
ねじ止め剤
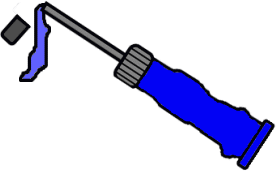 |
締め付けたねじが緩まないようにする接着剤のようなものです。但し他の材料同士を接着する力はありません。
ねじ部に塗ってからはめ込んだり、締めたナットの上から流し込んだりして使います。
高専ロボコンの本番の時以外では必要ないと思います。使うと良くも悪くも外れにくくなるので、一番最後に付けましょう。
使うとねじにこびりついて面倒なので、個人的に嫌いです。 |