基本的なけがきの仕方
|
| 〜線を引く〜 |
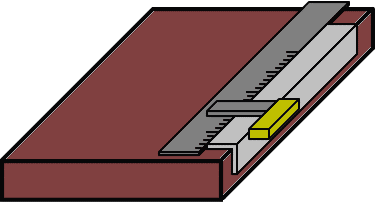 |
アングルの場合は、作業台の角に部材を当てて鋼尺とスコヤは右図のように当てます。ちなみに左利きの場合、スコヤの向きは左右逆の方が使いやすいと思います。 |
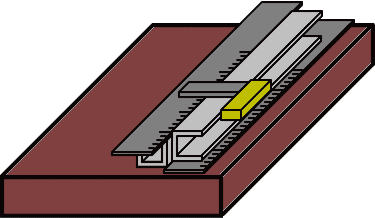
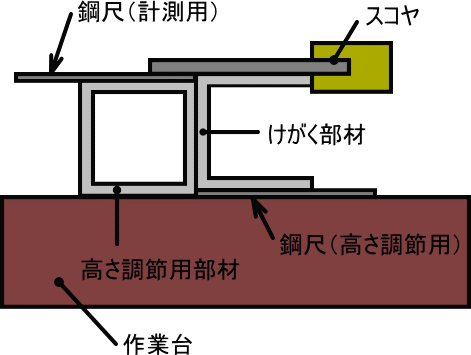 |
チャンネルや角パイの場合、2本の鋼尺と、けがく部材と同じ高さの部材を1本使って右図のように組み合わせます。こうするとスコヤを当てたとき、けがき面と鋼尺の高さが同じになるので、正確なけがきがしやすくなります。 |
| 基本的な手順 |
- まず材料を固定し基準となる線を引きます。普通は作る部材の片端を基準線にします。
※線を引くとき、けがき針で何度も引っかくと線が太くなったり二重になったりして見づらくなり、精度が落ちます。力を入れ過ぎてもやはり線が太くなったりバリが出て見づらくなったりします。力を適度に抜いて、一気に引ききりましょう。
- 基準線に鋼尺の目盛を合わせます。目盛は自分にとってけがきやすい位置で構いませんが、鋼尺の0mmの位置は摩耗や歪みによって狂っていることが多いので、避けた方が無難です。
- けがく寸法のところに軽く印を付けます。この時にそのけがき針のくせをつかみましょう。
- 印に合わせて直角に線を引きます。
※印をいくつも付けてから線を引くと、傷と印を間違えたりします。また、精度も落ち、ミスに気づいたときの被害が大きいので、1つ印を付けるごとに線を引きましょう。
- けがき線を引くとき、鋼尺の目盛の溝にけがき針を入れて引くのは絶対に止めましょう。
目盛が削れて見にくくなったり、精度が落ちたりします。
- 一度基準線に合わせた鋼尺は、できるだけ動かさないようにしましょう。線を引くごとに移動させると小さな誤差に気づかず、それが蓄積して最後には大きな誤差になってしまうことがあります。
|
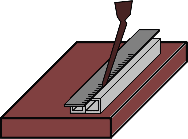 |
- 中心線を引くときは、部材の両端と間の数カ所に印を付けて、鋼尺を当てて慎重に引きましょう。補助の部材を使うと引きやすいです。
- ハイトゲージやトースカンを使うときれいに引けますが、数が少ないので、順番待ちで作業が止まるようなことのないようにしましょう。
|
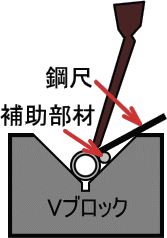 |
- 丸材をけがく時は、左図のようにVブロックを使い、鋼尺の下に補助部材として細い丸材を当てると作業が楽です。
- 初めに中心線を引きましょう。
- ステンレス製の材料はけがき線がつきにくいので、マジックか青竹を塗っておくとよく見えます。
|
|
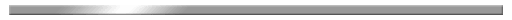
- 板材をけがく場合、けがき方は紙にペンで図を描くのと大して変わりません。紙の代わりに板、ペンの代わりにけがき針、円を描く場合はコンパスの代わりにパスを使うというだけです。
- 大きな円を描く場合、中心となる点にポンチを打っておくとパスがずれにくくなります。
- まっすぐな辺にスコヤを当てて、無駄ができるだけ出ないよう巧みに描きましょう。
- 無駄を可能な限り省くため、けがく材料はできるだけ短いものを選び、けがく部材は最も大きいものからけがいていきます。廃材を漁るのは面倒ですが、がんばりましょう。また、相当力がかかるパーツでなければ、ビス穴以外の穴が空いていても気にする必要はありません(軽量化のために、部材を穴だらけにすることもあるほどですから)。マジックで印でも付けて、使ってしまいましょう。
- 1本の材料に複数の部材をけがく時、部材同士の間に鋸の切りしろを空けておかないと寸法が合わなくなります。もっとも、部材端面までの正確な距離が必要になることはあまり無いかもしれませんが。
|
| ポンチの打ち方 |
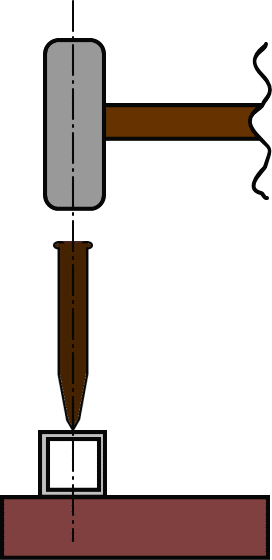 |
- アングルの場合は線引き時と同じように台に引っかけた状態でポンチを打ちます。チャンネル、角パイの場合は周りの鋼尺や補助部材をよけておいた方がいいでしょう。
- ポンチを打つ場所にはあらかじめ十字に線を引いておきます。通常は前項で描いたけがき線と中心線です。中心線の位置ではないところに穴を空ける場合は、その線を別に引く必要があります。
- 線の交点にポンチの先を合わせ、ポンチを垂直に保ったまま、ハンマーポンチならハンマーで叩き、機械式ポンチならそのまま押し込みます。
- ハンマーは垂直に打ち込むようにしましょう。また、ポンチが傾くとずれるので気をつけましょう。
- 中心線を引くのは面倒ですが、さぼると穴あけの時狙いを定めづらくなります。
- ポンチを強く打ちすぎると材料が歪み、見た目や精度が悪くなります。ずれたときの修正もしにくくなるので、やさしさを込めて(?)打ちましょう。目安としては、ポンチの凹みがt1mm材の裏から見えないくらいで大丈夫だと思います。
- 特にチャンネルの横の面に打つ場合はかなり力を加減しましょう。注意しないと歪みを通り越して曲がります。
- 板材へのポンチは強すぎると板が反ります。補強のために入れたプレートのせいでフレームが歪む、なんてことのないようにしましょう。
- 間違えてけがいた場合は、その線、あるいはポンチ穴を斜線で消しておきましょう。
|
|
|
|