主要な部材の製図方法
|
ロボ研の主要部材の製図をする際、覚えておきたい基本的な描き方を挙げておきます。必ずこの向き、描き方に従わなければいけないということはありません。この方法に従うとかえって見づらい図面になってしまうこともあるので、参考程度に覚えておいてください。
また、このページに書かれていることがロボ研以外でも通じるとは限らない・・・というより、一般の設計製図的には間違っているやり方が多々あります。
ロボ研専用の製図方法だと考えてください。 |
アングル材 |
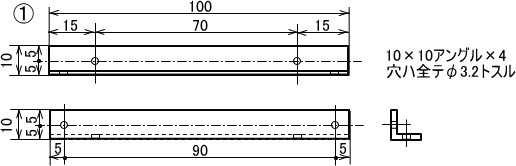
|
恐らくこれが「ロボ研的に最も正式な設計図面」と思われます。基本的には先に挙げた製図のルールに則っています。
- 左上の①は部品番号です。一つのセクションのパーツに通し番号を振っておくと便利だからです。用紙の端の方には、どのセクションのパーツ群なのかを明記しておきましょう。
- ロボ研の部材にビスを通す穴を空ける場合、大抵はφ3.2のドリルで穴を空けます。ビスの径がφ3.0なので、3.2であれば多少のズレを吸収できるからです。このように、あらかじめズレを想定して大きめに空けた穴を「バカ穴」と言います。ギアボックス軸などの穴あけではズレが許されないので、バカ穴ではなくビスと同じ3.0のドリルを使うのが常識です。
- この図面ではすべての穴がφ3.2ですが、違うサイズの穴がある場合「指示ノナイ穴ハ全テφ3.2トスル」などと記述します。
- ロボ研の図面では各寸法と全体の寸法を普通に全て記入していますが、正しい設計製図の場合、1方向の寸法の中であまり重要でない寸法1つを括弧でくくります。どんなに腕の立つ作業者でも誤差は出ますから、どの部分の寸法を重視すればいいのか-全体の寸法か、穴間の寸法かなど-を、はっきりさせておく必要があるのです。
- なぜわざわざ隠れ線のある面を正面図にしたのかと思うかもしれませんが、これには訳があります。アングル材をけがく(加工のための印付け)とき、ぐらつかないように机の角にアングルを当てます。それで上の正面図の方向から部材を見ることになるため、図面を上下逆にしたり頭の中で反転させたりする必要がなくなり、作業が楽になるのです。
さて、上の図の中には必要でない図や寸法があります。
まず側面図です。この図から読みとることができるのは、この部材がアングルであることと、どちらの辺にも穴が空いていることだけです。穴が空いていることは残りの図から分かりますし、「10×10アングル」と記述されているので側面図がなくてもアングルであることは分かります。ですからこの図は不要であると言えるでしょう。
また、部材の幅を示す寸法も必要ないでしょう。「10×10アングル」ですから、合計の幅が10mmになることは分かっていますし、穴は中心線に沿って空けられているので端からの距離が5mmずつであることも明らかです。 |
チャンネル材 |
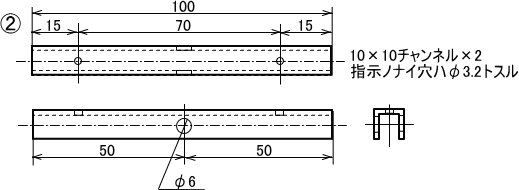 |
基本的にはアングルと同様です。チャンネルの場合、上のような向きで描かれることが多いです。側面図はやはり通常必要ありませんが、部材の向きを分かりやすくするため上の図には側面図が描かれています。
φ6穴の引出線の先には、スペースが小さかったので矢印を省きましたが、矢印を入れるのが正式な描き方です。ただし、製図は見やすいことが大切なので、間違える心配がなく、書き入れるとかえって見づらくなるようなら省いてもかまわないでしょう。 |
その他の部材に関しては上の2つを見れば分かると思うので省きます。
先にも書きましたが、この描き方は規則ではありません。上の図で平面図になる方向に穴がたくさん空いている場合など、例外も多くあります。あくまで「どうすれば分かりやすいか」を重視した製図を心がけましょう。 |
|
|